2015.5.1-2015.11.25
twitter夢垢、tumblrで呟き溜めたSS集。多少の加筆修正済。
上に行くほど最近のお話です。直で飛びたい方は下のリンクからどうぞ。
★:糖度30%以下
月の裏側 |
生きているだけマシだと |
私を閉じるくらいなら : 英
ひかりの割れ目 |
迷える貴方★ : 尼
お行儀良く : 勃
似て非なる★ : 普
|

|
酷い欠伸だ。私はむっとして彼に鋭い眼差しを向けるも彼はただ微笑ましい顔をして私を挑発する。「どんな形でも俺に意識を向けていてくれることが本当に幸せなんだ」などと不幸な男を演じる彼は確かに可哀想な境遇を経てきてはいる。しかし同情といった媚びた感情を持たれるのは嫌がるので、私は仲の良い知人になりきって女神の対応をするのだ。
「アーサー」
「ああ、それだ」
突然彼は子供のように喜んだ。
「誰の目にも見えない者に呼ばれるのはしょっちゅうだが、誰の目にも見えるお前みたいな者に名前を呼ばれるのは久しぶりだ。これから先百年分の運を使い果たした気さえする」
何を言っているのか分からない。確かに彼は、頭なのか網膜なのか真相は謎だがとにかく他の人とは違う。それでも、私以外とも十分交流しているように見える彼が何故そんな寂しいことを言うのだろうか。
「百年先も、アーサーは一人なの?」
「もって何だよ」
「だって、そんなようなことを言うから」
私は唇を噛んだ。本当に言いたいのはこんなことではないのだ。
「俺は、口説いたつもりだったんだがな」
彼が溜め息を吐く。
「分かりづらいよ。でも寂しさを埋める足しにはなるかもしれない」
「俺が?」
「ううん、私がよ。私が、アーサーの寂しさを埋めるわ」
「そうか」
また彼が笑った。
「俺は、寂しかったのか。それを分かってくれたのは、だったんだな」
「泣いてるの?」
「欠伸だよ」
それきり彼は大人しく私の肩に顔を埋めている。私は彼の頭を撫でながら、彼の睡魔の妨げにならないよう吐息を安らかに保ち目を閉じた。
|
□□□
|

|
「頭、おかしいんじゃないの」
どの口が言っているのか。俺は熟れた赤い唇を食べた。温かくて湿っていてぬるぬるしている。卑猥だ。実に卑猥だ。
「動物でしかないんだね、ブル君も。一人の女の前では馬鹿になるのね」
「日本では人間も動物に含まれるって聞いたんだわ」
ちゅ、という音が鼓膜に響いて脳を痺れさせた。彼女はまた何か喋ろうとするが、すかさず俺が言葉ごと飲み込む。彼女の背に手を回してより密着すると、主張し始めた俺の下半身が彼女にぶつかった。スラックス越しのそれは、けれどよく分かるくらいに俺の熱そのものだった。
「…頭、おかしいんじゃないの」
再び彼女が言う。もはやどうでもよい。
理性的な性欲というものは果たして存在するのだろうか。恋人の前ではにこやかな笑顔を携えて、誕生日にはプレゼントをやって、予約が取れない高級レストランでプロポーズをして、真っ白なウェディングドレスを着せて、可愛い子供を作って。そんな典型的な毎日を享受するための偽善的な性欲なら、生憎俺は求めていない。そんな普通の、ありきたりの幸せを極上の幸せと呼べない俺はきっとまだ若い。だけど間違ってはいない。好きな女がいて、頭の中が彼女でいっぱいで、どうやって組敷くか毎分毎秒考えて、めんどくさいと思うのに離れがたくて、何故好きになったのか自分自身に問い詰めて、言葉のある答えが出なくて。糞みたいな堂々巡りが一生続いてもまあしょうがないなと笑えるくらいには、の存在が俺の安寧を保っている。他の人が見たら馬鹿げていると思うだろうし、軽蔑されるかもしれない。だが、彼女たる存在は彼女ただ一人で、小難しい哲学さえ入る余地がなく、だからこそ俺達と外側の世界の間には何一つ阻むものがない。それが心地よい。
「鏡をよく見てきなさいよ」
彼女の瞳に俺が写る。淀みのない湖に、案外まともな顔の自分がいて思わず笑った。
ただ一人の女に馬鹿になれる。そう思わせてくれる彼女が、好きで好きで堪らない。
|
□□□
|
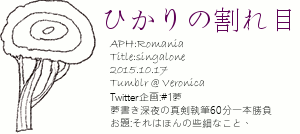
|
例えば彼女のツボのどこかに偶然であってもはまった時に彼女が他人に見せてしまうような素の笑顔や、セックスの時の薄く開いた唇や、我慢の針が振り切れて涙腺が決壊した時の泣き顔さえも、自分のものにしたいと思うのは、度の過ぎた愛情だと考えている。そう自覚はしているが、しかし持ってしまった以上はおいらの身体に巻き付いて離れてはくれないし、彼女に会う度にますます好きになる重症な恋心は肥大しておいらの脳味噌を圧迫するばかりだ。つまりは解決策がない。これを生かしてもなくしても、おいらはおいらでいられなくなってしまう。大事にしたいし独占したい。こんな相反する望みに相応の答えを出せる程おいらは達者じゃない。ただ彼女の声色にいちいち靡いて、熟れた心臓を差し出して彼女の好いてくれる笑みを絶やさないよう必死になるだけだ。
おいらには余裕がない。
「ブルガリアと何話してたの」
会議の合間においらの目の前でとその隣のブルガリアが何かひそひそと話をしていたのを、おいらが見逃すはずはなかった。彼の上司との上司は最近仲が良く二人が会う機会も前よりずっと増えたらしい。それは別に構わない。ブルガリアが羨ましいとは思うけど仕事とプライベートは違う。しかし、わざわざ会議の合間に二人で話す理由とは何だろうか。仕事のことなら後で仕事としてやればいいのに。お前達の上司なら今大変仲が良いのだから会合なんていくらでも設けられる。何故、しかもあんなに楽しそうに、何を、話していたんだろう。おいらはどくどくと煩い心臓に素直に従い会議終わりの彼女の腕を引いた。きょとんとした顔のに色んな気持ちが交錯するも、どれも外には出てこない。彼女に触れている手にじわりと汗が滲み出る。まさか、私生活でも密になる気ではないのか。ブルガリアはおいらの友達で、はおいらの一番好きな恋人で、けれど二人が仲良くなるのは何だか解せない。ブルガリアが彼女に抱いている魂胆とは何だ。彼女が彼に可愛い笑顔を向ける真意とは何だ。
度の過ぎた愛情なのは、分かっている。それでも知らずにはいられない。死に値しうると理解していても、肥大する恋心を愛せずにはいられない。
「そんな風に見てたんだ」
「そんな風?」
「何も、ルー君が心配するようなことも、話も、してないよ」
「……」
「信用できない?」
「…」
「困ったね」
そう言って、彼女の方が困ったような笑顔でおいらの手を握る。おいらは恥ずかしくなって俯いた。全部見透かしたの器の大きさに、少し罪悪感を覚えた。
彼女がおいらの耳元で誰も見てないよと助言をする。
不貞腐れた子供の如く、おいらは彼女を精一杯抱き締める。そしてが嬉しそうにした。おいらはこっそり唇を噛む。
おいらはいつになったら達者になれるのだろうか。絡み付いた厄介な愛情を綺麗なものに書き換えられるようになるのは、いつか。
|
□□□
|
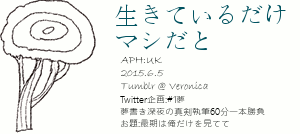
|
涙が溢れて止まらなかったのは、多分機内が酷く乾燥しているせいではない。夜明けの、太陽が滲みながら生まれる姿が窓の外に広がっていた。暗い青の中には眩い白い光と自然的な配列で並んだパレット。とても綺麗で、気を反らすようにアーサーが横からそれを指差した。生憎、私は涙で目を塞がれてそれどころではなかったけど。
そのうち目の奥がツンと刺されるように痛くなって、今度は機内の乾燥のせいで目が開けられなくなった。必死に流れる涙は私の頬を通って落ちる。目薬を差そうにも、目薬を待つ間さえ目を開けているのが辛い。思わず痛いと連呼した。
彼が労るように私の頭を撫でる。私は目に力を入れて、更に痛みを和らげようと手で押さえた。指先から、心臓の動く音が聞こえる。
やっと目が開けられるようになって、無様に溢れた涙をそっと拭った。ハンカチを使わなかったのは、必要な涙まで吸ってしまってほしくなかったからだ。さっきみたいな激痛は二度と経験したくない。ぱちぱちと瞬きして大丈夫だということを確認して、読むのが途中だった新聞に目を落とす。
「誰も悪くない」
隣でアーサーが私だけに聞こえる声で言う。何のことかと思ったけど新聞の見出しを見てよく分かった。彼は、私がこの記事のせいで泣いていると思っているらしい。誰も悪くない。悪くない。
突き刺さる文字は事実を淡々と記していて、連日世間を賑わせている私の国のことだった。これのせいで世界経済は今混乱している。立ち直れるかは、分からない。だってアーサーの言うように誰も悪くなくて、ただ幸せを求めて日々生きていただけなのだ。しかし、今思えば確かに、上手く事が進みすぎている節はあった。
でもそれに気付けたからと言って私や国民に何が出来たというのか。
「あとどのくらいか分かる?」
「二時間くらいだな」
「そう…ねえアーサー、私少し寝るから、着陸するちょっと前に起こして」
「分かった。今のうちに休んでおけよ」
私は地に這った植物色のブランケットを肩までかけると、ひっそりと瞼を閉じた。
飛行機はごうごうと凄い音を立てて目的地へ進んでいく。
隣に座るアーサーが眠った私に気を遣って頬に唇を寄せた。彼には他に意図があっただろうに、考えるのが嫌で、私は彼が私に気を遣ってキスをしたのだと思うことにした。
向こうのホテルに着いたらシャワーを浴びて、お詫びに彼に好きなように抱いてもらおうと、微睡んだ頭の片隅にその計画をしまいこんだ。
窓から少しずつ光が入ってくる。パレットが消える瞬間は近い。
|
□□□
|
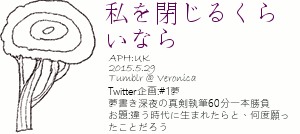
|
何故足は二本しかなくて、鈍足なんだろうと思う。地理的に陸路を行くのは難しい。いくら国家とはいえ砂漠や森に入ったきり行方不明なんてあり得ない話ではないのだ。
「また帰らなきゃいけないのね」
「不満ならずっとここにいろ」
「そんなこと出来ないって分かってるくせに。たまにはアーサーが来ればいい」
迫る船の時間に憂鬱を隠せない私に、空気が読めないのか皮肉なのか彼は淡々とした口調で続ける。
「お前のとこも、もう少しマシになればな…鉄道やら工業やら、問題は山積みだろ……って、レディが手を上げるなよ」
「鉄道が何よ工業が何よ。貴方のとこが異常なのよ。クレイジーって貴方の頭みたいなのを言うの」
窓の外の英国の香りを嗅ぎとる。これからまた暫く会えないであろう彼の温もりを忘れないように、思い出せるように、私は私の感覚器官に様々な角度で焼き付けた。自分でも大変健気な女だと思う。きっとアーサーは気付いていないだろうけど、気付かれてもからかわれるだけなので構わない。
「熱心だな。お前が俺の国の女だったら良かったんだが」
「…ふざけないでよ。それは言ってはいけない言葉よ。第一貴方の国の女性に失礼じゃない」
その場しのぎの駒だと言われたようで腹が立って早口で捲し立てると、アーサーが心外だという風に両手を上げる。まるで警官に銃を突き付けられたみたいだ。私を宥めようとする彼を無視して荷物を持つ。
「送るからちょっと待て」
「結構。さようなら。次に会うのは会議室よ」
「待てって」
信じられない力で性急に抱き寄せられると無理矢理唇を奪われる。私はこの国に来てからいつも絵に描いたような紳士に淑女として扱われていたので、咄嗟の反応が出来ずに暫くは彼の餌食になった。しかし力を振り絞って彼を押し返すとすかさず頬を平手打ちする。じんじんと手に痺れが広がるが、それよりも早くアーサーの頬に綺麗な赤い手形がついた。
「Ok, lady」
「…最低」
この時、私は本当に遊ばれていると思った。何かや誰かに寄り掛かって依存しないと生きていけない女に見られているのだろうか。正解だ。だって私は国として弱い。上司は味方といえど私が介入できることなど少なく、似た形で構成されているはずなのにどこかに一本線がある。だからこそ、船で何時間もかけて愛しい人に会いに来る。腰やお尻が痛くなって身体中バキバキになったとしても、ただ愛されるためだけに踵に靴擦れを作るのだ。
でもアーサーは違う。力があって富があって権力がある。だから私とアーサーは多分根本的に何かが違う。そして大きいものに巻かれるのは当然私だ。
もしいつか遠い未来に、私と彼が対等になれる日が来るのだろうか。その頃には、もっと簡単に会いたい人に会えるようになっているだろうか。私達は恐らくその瞬間にも生きていると思う。だけど、先の見えないことはやたら遠い。
「…悪かった。冗談だったんだ」
「それは何に対しての謝罪?」
「少しからかっただけなんだ。お前があまりにも真面目な顔をするから」
彼は困ったように笑うと私の手に大金を握らせる。チップのつもりなのか。笑えないブラックジョークだ。
「俺もたまにはそっちに行くことにする。でも、俺はお前がうちに来てくれるのが一番好きなんだ。が、ドレスの裾を引きずって俺の家の玄関に入ってくるのがたまらなく好きなんだ…」
そう言ってまた私を抱き締める彼が至極幸せそうに囁いた。
「俺にどんな我儘言ってもいいから、金も俺が出すから、俺に会いに来て、俺に好きだと言ってくれ」
何故足は二本しかなくて、鈍足なんだろうと思う。もし私が足よりも強くて速い何かを持っていたら、私の恋心はひとたまりもないなと恥ずかしくなった。
シェイクスピアを生み出した国の化身は流石と言うべきかフェリシアーノ達よりも女を口説くのが上手い。結局絆されるのは私だ。大量の錆びた色の紙を握り締めて、私は彼の耳元で生温い息を吐く。
|
□□□
|
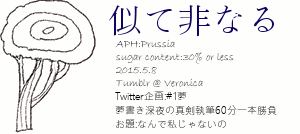
|
言葉は彼の唇から溢れて下に落ちた。まるで夢の中にいるような微睡みとぼんやりとした視界、嘘みたいな時間の配列に戸惑っている間にも上司たちは話を進めていく。
「消えるかもしれないって本当なの」
上擦った声がきっと彼の鼓膜を不快に揺らしたんだろう。情勢が少しも読めない程、私は国として落ちてはいない。それでも平静を装うなんてとても出来なかった。
「それ以上訊くな。俺様にだって分かんねえ。それよりお前は自分の中をどうにかしろよ」
私は絶句した。貴方にも分からないことって何?どうして自分の心配をしないの?私は込み上げてくる叫びを無意識に殺した。分かってる。分かってた。いつか私達みたいな存在に訪れるであろう日のことを知らないはずがなかった!
「情けない顔するなよ、国民のためだ、だけど決して大義じゃねえ。そんな崇高なもんじゃない。俺は俺でしかない。けどな、ヴェストには出来ないことがあるんだ。お前なら分かるだろ?そしてお前が俺なら、同じことをやるはずだ。国民のために」
ええ、勿論、私だって国民を愛している。替えがたい私の地肉、声、感情、心臓。たとえ愚かな歴史を繰り返しても、それでも大事なものよ。だけど、だけどねギルベルト。私達は限りなく人間に近く生まれてしまったのよ。そしてそれは、私達が国民を愛する気持ちと同じように事実で、未来永劫普遍なものなのよ。
「…俺は、お前やヴェストじゃなくて、俺で良かったと思った」
私の金切り声は窓ガラスを割ってしまいそうだった。彼は今日、あの腹の立つ笑い方をしない。上司に引きずられて家へ戻ってからは、化粧も落とさずに泣き喚くしかなかった。何故、彼だったのかしら。私はインプットされたことしかこなせないロボットのようだ。自分の終わりのことは、今までに幾度となく考えたのに。
|
□□□
|
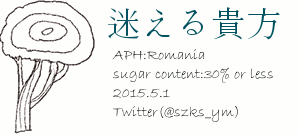
|
可笑しいと分かっていても手を出せないのがおいら達で、腐りかけた声帯で言葉を紡いだって届かないのは当たり前で、大切な人が泣いていても側にいられない温もりで、おいらは一体何なのか考えるのも煩わしい。
「笑って」
「」
「それだけで私は後悔なく死ねる」
だから、そちら側につくなと言ったのに。
|
□□□
|