 私は彼のものだ。 もっと正確にいえば、私は彼の一部だ。手や足といった具体的な部位を指してはいないし、一部といっても彼の意志の元、動いているわけではない。それでも私は大抵の場合、彼に従うのだろう。 「小柄で華奢で細くて豊かな栗色の髪の女の子がね」 彼の目が私を捉えた。突然何だとでも言いたげな視線。彼はいつも、お前は突然話し始めるなどとおかしなことを言って笑う。私は首を傾げていた。会話は突然始まるものではないのだろうか。思い付いた時、思い出した時に、話がしたいと感じた時に始めるのだから、会話の始まりはいつも突然だ。 「アントーニョのことをずっと見ているの」 だがおかしな彼のことなど今は置いておいても良い。今一番の問題は私の発した言葉の中にある。私はつとめて平静を装って続けた。 「彼女、貴方のことが、好きみたい」 心当たりはある?できるだけ穏やかに問えば、彼は顎に手をやって唸った。嘘が下手なのですぐ分かる。そして彼は、自分のそういう性質をよく知っている。 「…私、すごく嫌だったわ」 「そうやろな」 「簡単に流そうとしないでよ。逆の立場なら、どう?私に熱い視線を送る男を見てしまったら、どんな気持ち?」 冷静でいなければならないのに、思い出すだけでぞわぞわして気持ちが悪くなる。あれは多くの人間が美人の部類に入れるような端正な顔立ちの女だった。加えてか弱くて儚いなりたちで、中身が無いのに自尊心だけは高い男がこぞって手を伸ばすような女。自分の魅せ方を感覚で理解している狡猾な女。そんな女が、自分の立場も弁えず、物欲しそうな目でアントーニョを見つめていた。 「…心配せんでも、俺との考えてることは同じや」 「……」 「可哀想になあ。俺なんか好きになっても、報われるわけない。ただでさえ短い命を嫌な音で削り取っていくだけや。こう、きりきりきりーってな、身体の奥から寒気が駆け上がる、不快な金属音に似とる」 「うん、そう。貴方の言う通りよ。絶対に報われない気持ちを持ち続けるのに、命以外の燃料なんてあるはずがない。命を削り取る音が高い金属音に似ているのは、それが文字通り危機だからよ。これは駄目、これをしてはいけないって、身体から発する無意識の警報なのよ。だって私達とあの子は違う!日々を歩んで人生を作る過程が、木材のようにあたたかいわけがない!」 「」 アントーニョが私の頭を撫でた。 「羨望は捨てるんや」 羨望?これは言葉の暴力だろうか。後頭部をガツンと殴られた衝撃で死んでしまいそうだ。そうか、確かに羨ましいと思ったことはある。毎日を高速で走り抜けていくのに、笑顔を絶やさない彼らに。だからこそ大切で、大嫌いだった。私に、私達に、ないものばかり、持っている。 「…もしその女が何か仕掛けてきたら、ぶちのめしてあげてね。馬鹿だな、たった一つしかないその命だけで、俺達の無限の生を匿うことは無理だって、教えてあげてね。約束よアントーニョ」 「はは。ほな、土色の髪の図々しい女には注意しとくわ」 「栗色の髪の女よ。人の話、ちっとも聞いてないんだから…」 「なあ、?もっと素直に、我儘言ってええんやで」 「素直に我儘をなんて、なんだか変な言葉の組み合わせね……でも貴方がそう言ってくれるのなら、努力するわ」 「うんうん、ええ子」 私は彼の耳元に唇を寄せる。彼の意識がそこに集中しているのが分かって、こちらがどきどきしてしまう。ああ、私は彼の一部なんだと、実感する。 「…本当に好きなの」 「知っとる。俺にはお前だけや。…可哀想な子には、あの嫌な音を聞かなくてええように精一杯頑張ってもらうわ…も、手伝う?」 頷くと、アントーニョの手が私の背中を滑った。 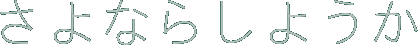 2017.5.6 material:伝染病 |