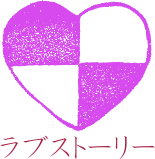
|
俺が瞳を覗いても、そこに映るのはいつだって俺ではない。 それに気が付いた時、頭を鈍器で殴られたかのような衝撃でぶっ倒れるかと思った。心臓を鷲掴みにされて、うまく息ができなくて、人間が死ぬ時はきっとこんな苦しみを全身で味わうのだろうと柄にもなく想像してしまう程だった。ただただ辛い。こうなることくらい予想できたはずなのに、どこかで良い結果を期待していたようで、その部分が無駄に大きすぎた。 「今日もよろしく、アーサー」 初めて見る色のスーツだ。よく似合っているのにくだらない皮肉しか言えないこの口を縫い合わせてしまいたかった。そんな馬鹿な俺にも何の悪意もない笑みを向けてくれるは本当に良い奴だ。良い奴なんだ。人としても、女としても。 想いを募らせるようになったのは二世紀以上も前だ。当時の常識からすれば彼女は女を逸脱していたが、今思うとそれは現代を先取りしていたというか、一歩先を行っていた。好奇は尊敬に変わり、その後すぐに恋慕へと塗り替えられた。 言葉にするのも恥ずかしい恋心を燻らせている時、真実は残酷に俺のそれを抉った。俺がやっとの思いで彼女の瞳を覗き込んだ時だった。 俺は彼女の正面に立っていたのに、彼女の目に俺は映っていなかった。 「…アーサー、すごい汗」 頭が痛い。俺を心配する彼女の声が確かな質量を持って俺の耳から体の中へ侵入する。彼女はポケットからハンカチを取り出して、俺の前髪を優しく掻き分けて汗を染み込ませる。 俺を見上げるの瞳には、生気のない俺が映っていた。 何で、こんな時に限って。 分かってるんだ。そんな風に映ったとしても、本当は彼女の視界にも入っていないことくらい。 やめてくれ! 「…」 俺は疲れたように彼女の名前を呟く。日頃暴力的なはずの俺の思考は、けれど惚れた女を殴ることはなかった。俺もこんなものを持っていたのかと笑ってしまう。屈辱だ。やりきれない思いがドロドロと溢れてくる。涙が出そうだった。 「アーサー、辛いの?」 ああ、そうだ。お前といると、お前の声を聞くと、お前のことを考えると、ちぎれてしまいそうになる。 彼女のにおいが近くで香る。 なあ、俺がお前の視界に入るには、俺は何度お前の瞳を覗き込めばいいんだ。 「、肩を貸してくれないか…」 彼女は頷いて、その華奢な身体を差し出してくれる。彼女に触れられるのはこれが最初で最後の機会だと思って、しっかりと噛み締める。 具合の悪いふりをして、彼女の優しさに縋る。が医務室の場所を訊いてきたが、俺は答えなかった。 |