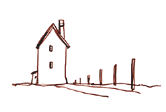
喉が嗄れる頃
2016.3.15

国家そのものであるというだけで、姿形は同じなのに人間とは異なっていた。自分に限らず国家なんてものは皆大体そうなのだという。その上自分には、国民性と言うに相応しい力も備わっていた。魔法が使える力。一時期はヨーロッパ中で酷く忌み嫌われたそれは、今となっても信じられている半面畏れられている。おいらは首都にある家の他に、田舎の方にもう一つ、別荘とは呼べない程の質素な家を与えられていた。国が安定している時は首都の家で過ごすが、そうでない時や魔法について何かをする時は自ら田舎に引っ込む。上司がどんな理由でその田舎の家を与えたかは分からないが、都合がよかった。自分達に出来ないことをやってのける他人程、気味の悪い存在はない。仕方がないのだ。
そんなわけで一人自宅に籠って魔導書を読み漁っていると、時間なんてあっという間に過ぎてしまう。腹が減るだけで食べなくても死なない。ご飯を抜いたこともあった。やはり死なない。始めこそ腹の虫は煩く鳴いていたが、無視し続ければ請う元気も失せたらしく黙った。秘書は休暇中で暫く会っていない。
「ルー君、ルー君ってば」
女の声がした。とうとう幻聴まで聞こえるようになったのだろうか。おいらは自分の身体を存在意義ごと憂えた。
「ちょっと、聞いてるの?」
「……」
「目が死んでる。大丈夫?」
女がおいらの頬を撫でる。心配そうな声色とは裏腹に彼女は無表情だ。
「どこから入ったの」
「鍵を閉めないなんて、不用心すぎるわよ」
「そういえば閉めた記憶がないや…」
「…本当に大丈夫?」
「」
おいらが彼女に手を伸ばす。すると彼女はさっと身を引いて一歩後ずさった。
「酷い臭い」
「何?」
「…水浴びしてる?」
「……」
「信じられないわね」
が呆れたように溜め息を吐く。それにちょっとむかついて、おいらはわざとらしく不貞腐れた。
「水浴びなんかしなくても死なないよ」
「生きるか死ぬかの問題じゃないのよ。臭いのよ。せめて体くらい拭いてよ。それから服も着替えて」
「今忙しいから後でやるよ忠告ありがとう」
「客が来てるっていうのにお茶も出さず死にかけてるだなんて。これ以上の醜態を晒す気?」
舌打ちして立ち上がる。彼女の方を見ると満足げで益々苛ついた。ああ、くそ。体が綺麗でもっと体力があったら今すぐここで床に押し倒すのに。それが出来ないのは男としてのプライドと、少なからずを大事にしているこの心のせいだ。まったく面倒なものばかりおいらの手の中にある。どう足掻いても捨てられないのは分かってる。
そこでふと面白いことを思い付いたおいらは、なるべく自然に、彼女に提案した。彼女が少しでも困れば大成功だった。
「じゃあ、も手伝ってよ」
すると彼女は一瞬ぽかんとした顔でおいらを見つめてから、肩を竦めて意地悪い笑みで承諾してしまった。

彼女の手伝いは、その意地悪い笑みに恥じないものだった。軋む木の台に乗って容赦なく上から水をぶっかけてくる。まだ日が高いとはいえ、市街地よりも標高の高い場所に建つこの小屋の周りは少し肌寒い。おいらは水をぶっかけられた後冷たい風が当たる度にブルブル震えた。しかし、目の前の悪魔はそんなことお構いなしだ。
「…こんなに水を浴びたらおいら病気になるかも」
「懐かしいわね。一体何百年前の話かしら」
「そんな昔の話じゃ……寒いよ」
おいらもいつか家の中に水浴び場が欲しい。こんな田舎の、ほとんど隔離用に与えられた小屋の水浴び場なんて後から取って付けるしかなく外にある。おいら達をぐるりと囲むように備え付けられている木の板は裸を見せないためでしかない。それでもこの水浴び場から小屋の中に戻るにはどちらにせよ全裸で移動しなければならない。狭すぎて、横に着替えを置くと一緒に濡れてしまうのだ。木の板のてっぺんは今のおいらの背では届かないし、木の台は怖くて乗れない。はおいらよりも軽いし度胸があるから乗れるだけだ。この小屋はちょっと間抜けな造りだと思う。まあ、今日はが手伝ってくれるから変質者にならなくて済むけど。
「そういえばさ…何とも思わないの?」
「何が?」
「この状況」
「だから、何?綺麗になって良かったじゃない」
「そうじゃなくて、おいらの裸を見て何とも思わないのかって話!」
「…別に、男の身体なんて何ともない。戦場は不便だし何もないから、皆簡単に服を脱ぎ捨てる。私もそこにいるから、慣れるわ」
「ちょっと待って。お前、男の身体は見慣れてるってこと?」
が目を逸らした。背筋に悪寒が走り、同時に激しい怒りが内側から湧き上がる。彼女が慌てておいらをなだめた。
「大丈夫よ」
「何が大丈夫?自分が何をされているか分かってるの?それがどういう行為か知ってるのか!?」
「馬鹿にしないで、そんなことくらい知ってる!…彼らは強く優しい。彼らは私を抱いたりしていない。私のこと、女だと思っていないもの」
「…この際、男か女かは関係ないんだよ。自分より弱ければ簡単に捻じ伏せられるんだから」
「私は大丈夫よ。ちゃんと、皆から少し離れた所で寝ているし……だから泣かないで」
熱い涙が容赦なく目と頬を焼いた。が桶を置いておいらの濡れた頭を撫でる。おいらよりも小さい。細い指で、か弱い身体で、戦うことを強いられている女。
おいら達は一体誰のものだ。国家そのものであるというだけで、姿形は同じなのに人間とは異なっている。人間は下衆だ。おいら達を都合よく利用し遠ざける。その上くだらないもののために沢山の命を犠牲にし、愚かなことばかり何度も繰り返して、歴史から何も学ぼうとしない。他の動物よりもほんの少しだけ知恵があるだけだ。それと引き換えに失ったであろうものの方が偉大だとおいらは思う。神は何故こんなものをお創りになったのだろうか。何故こんなものにおいら達を似せたのだろう。
「ルー君、抱き締めてもいい?」
「…濡れるよ」
彼女は微笑みだけでおいらの罪悪感を包み込んで、それから今度はおいらを、まだ発展途上の身体から生える腕で抱き締めた。罪悪感、それは彼女を守り切れなかったことに起因する。物心ついた時から彼女を愛していた。同じように大きくなって、だけどいつからか性差が現れるようになって、おいらは。
そうだ。初めて人間に似て良かったと思えたのはその時だ。おいらとの差が、まるで本物の人間みたいで嬉しかった。寿命が来て、いつか死んでしまうと思えたのだ。

でも、だから何だって言うんだ。単なる錯覚で、おいら達は結局人間じゃない。人間は嫌いだけど国民を滅ぼしたらそれはもう自殺と同じだ。おいらを作っているのは国民と領土とその他諸々だから。
おいらを必死に抱き締めるが呟いた。
「私がもっと大きかったら、胸の中に閉じ込めて、ストーブの代わりになってやれるのに」
違う。違うんだよ。それはおいらの役目なんだ。勝ち目がないことは薄々感じてた。おいらは運もなければ力もない。自分自身のことも維持できない。だから負けた。こんな田舎に避難して魔導書を漁るしか能のない、つまらない男だ。一人で水浴びも満足にできない屑だ。神は何というか、やはり当たり前のことをしている。だって神は人間がいないと存在を認識されない。草や花や木や羊たちは、神のことも讃美歌も聖書も何も知らないはずだ。神が人間をお創りになったわけでも、それにおいらを似せたわけでもない。人間が神とおいらを創ったんだ。人間がおいらを人型にしたんだ。かわいそうな神。かわいそうなおいら。人間に何もかも握られている。自由は、ない。
「随分探したのよ。貴方の秘書は休暇中で会えないし、他の上司は皆口を揃えて貴方の居場所なんて知らないって言う。街も大人しくて、ルー君に何かあったんじゃないかって、私…」
「…上司は、おいらに興味がないから」
「そんなの間違ってる……でも、その方がきっと誰もが楽できるのね」
が背伸びしておいらに口付ける。彼女の唇は温くてほんのり甘いような気がした。おいらの濡れた前髪から雫が落ちて、の頬に落ちる。まるで彼女も泣いているみたいだった。
「…痩せちゃったね、ルー君」
「……」
「私、もっと早く来ればよかったね」
「…もう、十分だよ」
だってお前は今ここにいる。おいらを探して、おいらを見つけた。それだけで、紙よりも脆い精神は簡単にしわくちゃになる。強靭なはずの肉体が朽ちる。それは決して駄目になるということではない。
おいら達は人間に似ている。感情があって、欲望がある。無ければいいのにと思うこともあるけど、もし無くなれば彼女のことも忘れてしまうのかと思うと、結局は今の形に落ち着いてしまう。
おいら達に自由はない。だけど、この心は、この気持ちは、おいらだけのものだ。
「さあ、そろそろ中に入りましょう」
再び台に乗って木の板のてっぺんから布を取ったが、それをおいらの身体に巻いて手を引いた。彼女の着ている服はびしょびしょに濡れていた。だけど彼女は笑っている。その様子が何だかちぐはぐでおいらもつられるように笑った。思えば、笑い声を上げたのは久々だった。
「食材ってあるの?あるなら何か作るけど…口に合うように頑張って作るから、食べてくれる?」
「あるよ。食べられる状態かどうかは分からないけど、が作ってくれるなら腐ってても食べるから安心してよ」
「ちっとも安心できない」
着替えるおいらを置いて簡易なキッチンに入る彼女の背中をぼうっと見つめた。
この背中をいつまでも眺めていられたら。黙って欲に従うことのできる生き方を選べたら。
きっとその日が、おいらの身体の命日だ。