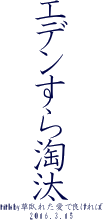 愛しているから、あなたを持て余すのが辛いから、あなたの元を去ろうと思う。 使い古された馬鹿な常套句は一体いつまで通用するのだろう。 割れた花瓶の破片を拾う彼女の手を払うと透明な砂がきらきらと零れ落ちる。何故、今だったんだろうか。 「アーサー」 「、」 やや大きな破片がの手の平を掠めて床へと吸い込まれていく。それは耳障りな音と共に足元でもう一度死んだ。彼女の手からは赤い血が膨らんで垂れる。俺は彼女を横抱きにして寝室への階段を上った。 「アーサー」 俺の腕の中で萎えたように呟く彼女の手の傷は、多分本当は大したことはないのだろう。ただ割れたガラスで誤って切ってしまっただけだ。それなのに、俺はこの世の終わりのような気持ちになって、寝室のベッドの上に彼女を座らせると階下へ慌ただしく降り、救急箱を持って再び階段を駆け上がる。 「…手を出せ」 ゆるゆると差し出された彼女の手は陶器のように白く無機質でまるで生き物ではないような感触だった。俺はその事実に顔を強張らせるが、揺れ動く心を隠すように彼女の傷口を消毒した。染みて痛いのだろう、眉間に皺を寄せたに、予想外の安堵が訪れる。何故だか分からなくてそんな自分に嫌気が差した。逃げるように視線を逸らして彼女のスカートの下の腿を想像する。俺に雄としての本能があるように、彼女にも雌としてのそれがあることにほんのり期待していた。 ***** 「その妖精さんとやらとを大事にすることでは、全く違うんだよ」 「うるせえ髭お前に何が分かる」 「ほら、汚い言葉使わない。も怯えてるよ」 淡い色で輝く妖精は、この髭に限らず世界各国の奴らに共通して見えないらしい。周りにも見えているのか、俺にしか見えていないのか、俺に判別できる能力は無く、昔から孤独だったことはよく覚えている。実の兄達でさえ、俺を煙たがっていた。 「、暫く会わない内に、随分アーサーに懐柔されたね。って!おい足を踏むな坊ちゃん!」 「お前の誤解を生む表現には心底呆れている」 「だって事実だろ!それにお兄さんは今と話してるんですー!ね、?」 「フランシスは相変わらずね」 「、こんな奴無視しろ」 「それは出来ないわ、アーサーの頼みでも」 「うわ、ってば可哀想!」 スカートの上で落ち着くの手の傷は大分良くなってきていて、俺は毎日傷口の経過を見ながら緊張の糸を徐々に緩めていた。今日は二人の休日が重なったので何をしたいかと彼女に問うたところ、フランシスの作ったお菓子を食べたいと天使の如き微笑みで俺を抹殺して今に至る。確かにこいつの作る飯だけは認めてやるが、の望みでなかったら何を好き好んで髭の家などに来るものか。が、しかし、俺の隣でにこやかに笑う彼女を見るのは俺の幸せであったので、彼女を見る度に口角が上がった。そしてそれを見逃さなかった髭がにやけるのを、勿論俺も見逃さない。 「破顔するにも程があるよお前。気持ち悪いな」 「お前の顔をワインボトルで殴ったらどんなに気持ちが良いだろうな」 「相変わらず酷いな、この海賊紳士」 「そこまでにしてよね」 の願いを聞いてやらないはずもなく、俺は髭に浴びせる罵声の代わりに彼女に愛を囁こうと試みる。どこぞのラテン野郎共とは違う、きちんと質量の伴った言葉を漏らす度に、が恥ずかしそうにするのがたまらない。 「おい、人ん家に来てまでイチャつくのはよせよ」 「醜いぞ髭。羨ましいのは分かるけどな」 「美味しかったわ、ごちそうさま」 が奴にお礼を言って俺の手を引く。白くひやりとした手に見とれていると、髭が彼女に向かってウインクしたのが目に入って吐きそうになった。 俺は何も気付いていなかった。 ***** 「暫く会えない」 彼女のクラシックなスカートが揺れる。俺は立つのもやっとな身体を無理やり起こした。 「アーサー、またすぐに戻って来るから」 いつだ。いつの話だ。百年後か。その時にはお前は俺を越えているのか。俺はどうなっているのか。俺達の「すぐ」はいつだって「すぐ」やって来る。だが、人間が生み出した言葉というものは、時折俺達とは全く違う次元の、時間軸のものだ。いや、俺達が異質なのか。とにかく、時間軸に関わる言葉は途方もない暗喩だ。 「愛しているわ」 途方もない。愛情を表す言葉も。曖昧で、信じがたくて、重苦しくて、待つことを強要される。 「貴方が居ない間、フランシスが私を助けてくれる約束なの」 フランシス。俺にやたら牙を剥いて、外見ばかり気にする、中身のない男。そんな男に懐柔されたのか、。俺が知らぬ間に、どこでそんな技を身に付けたんだ。 「貴方は少し、過保護すぎる。貴方は私の親でもなければ、私は貴方の子供でもない。私は陶器じゃないのよ」 どうして気付いてくれないのと、責められているような感覚。 彼女は確かに俺のものだった。俺だけが世話をして、愛して、可愛がって、守ってやれた。そうだ。彼女だけじゃない。何もかも、俺のものだった。それが今ではどうだ。財産の喪失は力のそれに比例し、面倒をみてやった奴らは次々と俺の元を去っていく。 皆口を揃えて言った。 「貴方は、好きでいるには申し分ない人。それはこれからも変わらない。だけど強すぎて怖い」 何も分かっていない。守り抜くには強さが必要だ。当たり前だろう。、お前だってそれを分かっているはずだ。 百年は長い。いつになるか分からないのに、俺はお前を待ち続けなければならないのか。兄達に疎ましがられながら、妖精達と他愛無い会話をするだけの、あの小さな頃に逆戻りしろと言うのか。 「貴方と対等になりたいの」 が俯いた。動機としては、何も問題なかった。 「俺も愛してるよ」 俺は慣れた仮面を被って紳士のふりをする。長い時間をかけて何もかも手に入れたはずの俺は、俺自身に蓄積されたものは何一つないことに絶望するしかなかった。
material:moss
|